焼香のマナー
仏式焼香(回数は、1回あるいは3回)
 |
| 1.合掌 |
2.香をつまむ |
3.額に香をいただく
※但し、浄土真宗はいただきません |
4.香炉にくべる |
5.合掌 |
6.一礼 |
|
正しい数珠の掛け方
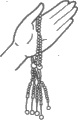 |
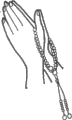 |
| 普通は数珠を二環にして左手に掛け、合掌します |
腕の前で堅実に合掌(浄土宗) |
|
遺族の仏式葬儀における宗派別正しい焼香の作法
浄土真宗本願寺派
左手に数珠を持ち、導師に一礼し、焼香すべき尊前に進み、ご本尊に軽く一礼します。右手に香をつまみ、いただかずに一回だけゆっくりと香炉に落します。数珠を両手にかけて合掌、お念仏、礼拝し二、三歩さがって導師に一礼し席にもどります。
真宗大谷派
左手に数珠を持ち、導師に一礼し焼香すべき尊前に進み、ご本尊に仰ぎみて、身を正し頭礼(軽く頭を下げること)をし、右手で香をつまみ、いただかずに二回香炉に落します。数珠を両手にかけて合掌礼拝し、二、三歩さがって導師に一礼し席にもどります。
真言宗
焼香は死者の得脱を祈念して、お迎えしたご本尊である不動尊に対して行います。左手に数珠を持ち、祭壇の前に進み、導師に 一礼してから焼香します。仏前に向かって合掌礼拝し、右手の親指と人差し指で軽く香をつまみ、額のあたりまで上げてから香炉に落し、再び合掌礼拝します。焼香が終ったら、導師に一礼して席にもどります。焼香の回数は真言宗では仏・法・僧の三宝にに供養すること、身・口・意の三密修行に精進すること、そして戒香・定香・解脱香といって、自分自身が戒律を保ち心の静寂を求めることが出来る功徳があるということから、焼香は三回行うほうがよいとされています。〔注〕しかし、必ずしも三回しなければならないということではありません。会葬者の人数や場所によって一回でもかまいません。要は、回数ではなく心を込めた焼香が大事なのです。
日蓮宗
左手に数珠を持ち祭壇の前まで進み、導師に一礼し、祭壇に向って合掌礼拝します。右手の親指と人差し指で香をつまみ、額のあたりまで上げ、静かに下げて香炉に落します。故人の冥福を祈りつつ、三回繰り返し、再び合掌礼拝。導師に一礼して席にもどります。焼香を三回行うのは、三宝供養といって、仏・法・僧を敬い、帰命することからきているとも、空・仮・中の三諦にならっているともいわれています。〔注〕但し、会葬者が多い時や場所の都合により一回で済ましてもかまいません。要は心を込めるということが大切なのです。
曹洞宗
数珠を左手に持ち、導師に合掌し一礼してから霊前の焼香台の前に進みます。合掌礼拝し、香を親指、人差し指、中指の三本の指でつまみ、額のあたりまで上げて軽くさげてから静かに香炉に落します。焼香の回数は曹洞宗の場合、お寺によってそれぞれの決まりや伝えがありますが香を二回たくのが普通です。一回目を〔主香〕といい右手の浄指(親指・人差し指・中指)で香をつまみ故人の冥福を祈りながら香炉に落します。
〔注〕実際の葬儀では、会葬者の人数や時間的な問題で一回で済ましてもかまいません。要は回数の問題ではなく、真心を込めて供養することが大切です。
浄土宗
導師に軽く会釈して霊前に進み、焼香台の前で遺影を見つめ合掌礼拝します。香をつまみ、額のあたりまで持ち上げ、ゆっくりと下げ香炉に落します。再び合掌礼拝し、一礼して席にもどります。回数については特に決まりはありません。三回の場合は仏・法・僧に捧げることを意味しています。二回の場合は仏と衆生に捧げるという意味や香 の戒香・定香になぞらえる意味といわれています。一回の場合は霊前を一心に清らかにするという意味があります。会葬者や式場の状況に応じて回数を選ぶのがよいでしょう。
神式(玉串奉奠)の作法
玉串は根元を右手、枝先の方を左手で受取り、右に回し根を祭壇に向けて置きます。このあと二礼二拍手一礼しますが、拍手はしのび手といって音をたてないようにします。
キリスト教式(献花)の作法
献花は花を右にして受取り、90度右に回し花を手前に、茎を先に持ちかえて献花台の上に置き、一礼して終わります。
参列のマナー
- 通夜、告別式のどちらに参列するかは、故人との交際の度合いで決めますが、親しく交際していたのであれば両方に出席するようにする。
- すぐに弔問できない時は、まず弔電を打ち、代理人を立てるなり後日伺うようにするなりして、電話でのお悔やみは避けます。
- 親族以外の通夜や告別式には子供連れはできるだけ避けたいもの。どうしてもの時は、予め子供にお別れの意味を話して、やたら騒いだり、泣いたりしないように気を付けさせましょう。
- 告別式では、焼香を済ませた後もできるだけ残って出棺まで見送ります。霊柩車に棺を納めるときは、黙礼をし、走り始めたら合掌や黙とうをしながら見送ります。
|